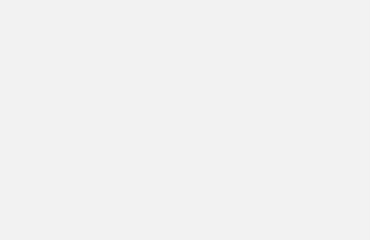おはよーございます。
今日は、地球の木さんhttp://www.seikatsusha.jp/chikyunoki/index.htmlで連載しているコラムのバックナンバーを掲載します!

前回は、「切れ味とはなにか」についてのお話でした。
ざっくり振り返ると、切った食材にダメージを与えない刃物が「良い切れ味」だといえる、という内容でした。
刃先がのこぎり状になっていたり、刃の側面が傷だらけになっている刃物。
それらが食材を傷つけています。

そういう傷を消すために、砥石(といし)を使って、包丁の刃を磨いていきます。
砥石(といし)にはたくさんの種類があります。
大まかに、粗さで別れていると思ってください。
紙やすりと一緒です。
数字が大きくなるほど、目も細かくなっていきます。
私が使う砥石は、
♯320
♯1000
♯3000
♯8000
♯10000
♯10000以上~(天然砥石)
と、たくさんの砥石を使い分けています。
どんどん細かい石で磨いていき、傷を消していくのです。
♯1000でつけた傷を♯3000で消し、♯3000で消した傷を♯6000で消し…
最終的には、♯10000以上といわれる、京都産の天然砥石で仕上げたりす場合もあります。
そうして粒子の細かい石で傷を消していくことで、「切れ味」の良い包丁は出来上がっていくのです。
「切れ味」の良い包丁で切ると、様々なメリットがあります。

細胞を壊しにくいので、余計な水分が出ない
苦み えぐみをが出ない
お刺身でしたら、生臭さ、魚臭さを感じにくい
切断面がなめらかなので、口当たりが非常に良い
食材が長もちする
食材の味が生きるので、調味料を減らしても美味しく調理できる
などなど…
いいことずくめです。
こんな素晴らしい結果をもたらしてれる砥石(といし)とは一体何なのか。
次回は、「砥石とはなんぞや」についてお話してみようと思います。
ご意見、ご感想等ありましたら,以下のメールアドレスからお気軽にご連絡ください!
駿眉-junmei- 佐藤翼 tea@junmei.info